庭に白絹病が発生しました。

庭作りや畑作業をしてきて初めて出会ったので、これが白絹病かぁ…という残念さとショックで気持ちが落ちていました。
というのも調べれば調べるほど「完治が難しい」「やっかい」などの情報が出てきたからです。
Instagramで投稿したことをきっかけに、たくさんのかたから情報を頂きました。
ネットで調べるだけでは出てこなかった対策や予防を知ることができたので、自分自身のメモ代わりに
そしてわたしと同じく、薬を使わず庭作りをしたいかたの参考になればと書き留めておきます。
白絹病とは
野菜や花、果樹などの株元や根に白い糸状菌が絡みつき、小さく丸い菌核を作り、植物を弱らせたり、枯らせていく病気です。

カビの一種のため、夏の高温多湿な時期に発生しやすくなります。
また好気性菌が原因で発生するため土の表面近くで活動します。
白絹病発生場所
わが家はグランドカバーとして育てているクローバーの一部で発生しました。
ありとあらゆる植物に感染する可能性があり、かかりやすいのがマメ科、ナス科、ウリ科の植物で、特にネギ、キュウリ、カボチャ、スイカ、トマト、ピーマン、落花生などの野菜に多く発生します。
わが家では観葉植物が一番最初だったので、発生したらその土を違う場所に移したりしないことが大事ということを痛感しました。
白絹病が発生したら?処置編
インスタやFaceBookの投稿に頂いた情報をまとめました。
- バーナーで焼く(冬に眠らせると春に爆発する)
- 石灰を撒いてPHを調節、草刈りをし、余力あれば溝を切り水分を調節する
- 熱湯消毒する
- 酸素が届きにくい土壌30cm以上に埋める
- 感染した植物は腐るため廃棄
- 菌には菌で対抗、納豆菌を有効活用
- 米ぬかを土に混ぜ込む
- 木灰や苦土石灰などアルカリ寄りのものを撒く
- 病気の株と周りの土を全て取り除く(広い敷地がある場合、隅に埋める)
- 木酢液を原液でかけたら消えた(初期段階のみ有効)
- 放線菌が生産する抗生物質「バリダマイシン」が、白絹病菌を含む糸状菌に対して有効→放線菌を増やすにはカニガラや米ぬかを活用
- 重曹をふりかける→一週間ほどで黒くなり、土も変えずに済む
土壌を焼くと虫や微生物も死んでしまうため抵抗があったのですが、頂いたコメント(昔から焼き畑があるように、火は全てを灰にしてリセットしてくれる)という文章を読んでなるほどと納得できました。
今すぐ焼くことを選択するわけではないですが、様子をみながら必要と感じたときには活用しようと思います。
わたしの対処も書き留めておきます。
- 発見直後、木酢液を薄めたものを散布
- 1週間経ち、広がりが大きくなったので、菌核、菌糸を撤去し、傷んでいる草の周りをお堀のように掘り、燻炭を散布

- アルカリ性のものを撒こうと、掃除に使用しているほたてパウダーを散布

- 米ぬかも散布して、黒マルチで覆い様子を見る

- 頂いた情報から納豆菌液を培養(詳しくはえひめAI項目へ)
- 黒マルチを取り、目立つ菌糸や菌核を取り、米ぬかをまいて様子を見る

- 完成した納豆菌液を希釈して散布

- 2月に作ったボカシ肥料を入れて耕す

ボカシ肥料は入れようと思っていたわけではないのですが、入れていた米袋の底が破れてしまったので投入してみることにしました。
ボカシ肥料には放線菌などが含まれています。菌には菌でどんな反応が起こるのか試してみたいと思いました。
ただし、未熟な有機物は逆効果だそうなのでご注意ください。

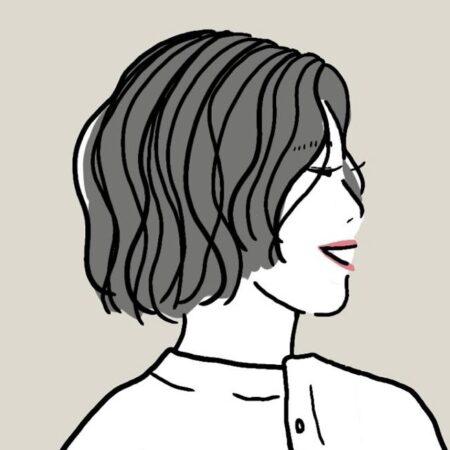
菌糸と菌核
取り除いた菌糸と菌核は発泡スチロールの箱に入れて、透明ビニール袋をかぶせて太陽消毒していました。

before
2週間の太陽消毒後↓

after
菌糸と菌核、かなり減りました。
このままの状態をもう少し続けてから、庭の隅に埋めようと思っています。
えひめAI-2
愛媛県産業技術研究所で開発されたもので、土壌改良だけでなく、水質浄化や消臭などにも効果を期待できる資材です。
えひめAI-1は産業用資材。AI-2は家庭用で、身近な食品で作ることができます。
「えひめAI-2」で調べるとたくさんの情報が出てきますが、わたしはInstagramで繋がっているmicoさんの投稿を参考にさせて頂いて作りました。
材料
- 納豆1粒
- ヨーグルト25g
- 砂糖25g
- ドライイースト2g
- 水450ml

全てを混ぜたら1週間ほど日当たりの良い場所に置いて培養するだけだそうです。

蓋をゆるく締めるか、布で覆って呼吸できる状態にするのが大事なポイントで、キツく締めていると爆発するそうなのでご注意を。
出来上がったら追記します。
植物だけでなく水回りのヌメリにも使えるってすごいですね!
白絹病を発生させないためにできること(予防編)
頂いた情報と調べたことを記しておきます。
- 有機資材の材質を追加する(笹の葉、イネ科の乾燥ものなど→菌類の単一化を防ぐため)
- 善玉菌(トリコデルマ菌)・ゼオライトの入った土壌改良材を用いる
- 連作を避けて麦類との輪作(順番に)をする
- 定期的な熱に夜土壌消毒と冬時期の天地返し
白絹病は気にしない・自然治癒を待つ(受容編)
インスタに投稿してよかったと思ったのは、受容派のかたの声を聞けたことでした。
虫に葉を食べられても気にしなくなってきたのに、菌が根にはりついてびっくりしていた自分に気づいて立ちどまることができました。
この情報は通常の検索では出てこないと思うので、必要なかたにとってかなり勇気づけられると思います。
皆さんの声
- 白絹病は空気中に存在しているので、どうしても出てしまう。特性を受け入れ、風通し、水分調整をして弱まるのを待つ。
- 毎年出て枯れてしまうものもあるけれど、復活する植物もある。乳酸菌や納豆菌をまいたこともあるけれど臭い。ほっときましょう!そのうち復活します。暑くてちょっと蒸れちゃっただけ。
- そこら辺に存在する菌なので気にしていない。
- 日本は高温多湿なので病気や虫とは隣合わせ・神経質にならなくても自然がバランスを取って解決してくれる。
- バランスと受け入れて何もしていない。周囲の草たちの元気が勝って白絹病で枯れたところをカサブタのように覆い、ほとんど目立っていない。
- 人が何か足そうとすればするほど悪循環を招く。自然が解決してくれるのを待つ。
たくさんの情報から何を選ぶか
どの情報も情報として受けとめて、何を選んでいくかは自分で決めることだと思っています。
同じことを試したとしても、庭や畑の状況はそれぞれ。
誰かが試して効果があったことが、わたしが試して必ず効果があるとも限りません。
なので、全ての情報に感謝をしながら、まずは目の前の土や植物の声に耳を傾けて、必要だと感じたものを試していこうと思っています。
つい「やれること全部試さなきゃ!!」という思考に進みがちですが、病院に行かなくなった自分自身をふり返ると調子が悪いときにまず必要なことって休むことなのですよね。
35度以上の気温が続いているのですもの、そりゃ土も疲れていて当たり前。
なのでゆっくり、土や菌の変化を楽しんでいこうと思います。
大事にしたいこと、握りかえせて本当によかったです。
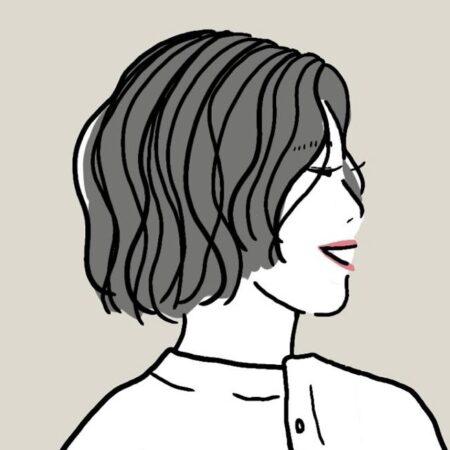
今後の変化や試してみたこともこちらに追記していきます。
追記しましたら、Instagramのストーリーズでお知らせします!







